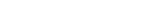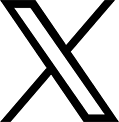RAKSULグループといえば、印刷ECサービス「ラクスル」の印象が強いでしょう。現在では印刷事業だけではなく、物流事業の「ハコベル」、マーケティング事業の「ノバセル」、ITデバイス&SaaS統合管理サービス「ジョーシス」、ホームページ制作SaaS「ペライチ」など、多方面で事業を展開しています。直近では金融プラットフォーム事業への参入を発表し、事業領域を拡大し続けています。
そんなRAKSULグループは今、共通ID「RAKSUL ID」を軸に、グループのサービスを横断する共通プラットフォームを構築し、顧客により一貫したサービス提供を実現する取り組みを進めています。
IT業界においても、この成長フェーズに差し掛かる企業はそう多くはありません。エンジニアにとっても、大きな成長の機会が広がる環境と言えるでしょう。
今回は、技術戦略の中核を担うグループCTOの竹内俊治さんと、3月から新たにジョインしたグループCIO(Chief Information Officer、最高情報責任者)兼グループCDO(Chief Digital Officer、最高デジタル責任者)の藤門千明さんの対談を実施。技術組織とテックビジョンについて語っていただきました。
※この記事はラクスル株式会社によるタイアップ広告です。
- 高い解像度で中小企業のビジネスを支援してきた
- “サイロ化”してしまった各サービスを「RAKSUL ID」で連携する
- サービス間の連携はトラブルや「空白地帯」が生じやすい
- 事業の深化と横断的基盤整備の狭間で「健全なコンフリクト」を起こす
- プラットフォーマーになる瞬間だからこその「挑戦しがいのある環境」
- 📢 RAKSULグループではエンジニアを募集しています!🌈

高い解像度で中小企業のビジネスを支援してきた
──まずはRAKSULグループ全体の事業について教えてください。

竹内 俊治(たけうち・としはる)
ラクスル株式会社 上級執行役員 グループCTO
2002年に東京工業大学大学院を卒業後、在学中から関わってきたコンピュータグラフィックスを手掛けるベンチャー企業に勤務。IPOを経験した後、2011年に楽天グループへ転職。海外赴任や複数事業の開発責任者を務めた後、ウェルスナビへ参画し、CTOとして成長ベンチャーの基盤・体制を強化。2024年2月より現職。
竹内俊治(以下、竹内) 当社は現在多くの事業を展開しています。祖業である印刷ECサービスの「ラクスル」から始まり、物流事業の「ハコベル」、マーケティング事業の「ノバセル」、ITデバイス&SaaS統合管理サービス「ジョーシス」、ホームページ制作SaaS「ペライチ」など、多岐にわたります。
これらの事業に共通しているのは、SMB(Small and Medium Business)、つまり中小企業のビジネスをエンドツーエンドで支援するということ。例えば、新たに店舗を開業する際には、名刺やチラシ、Webサイト、ハンコ、ユニフォームなど、さまざまなものが必要になります。当社は、そうした中小企業のビジネスを、ソフトウェアの力で効率化し、支援してきたのです。

藤門 千明(ふじもん・ちあき)
ラクスル株式会社 上級執行役員 グループCIO 兼 グループCDO
2005年に筑波大学大学院を修了後、ヤフー株式会社(現 LINEヤフー株式会社)に入社。エンジニアとして、Yahoo! JAPAN IDや決済システムなどYahoo! JAPANの多くのサービス開発やプラットフォーム開発に従事。2015年よりCTOとして全社の技術部門を統括し、2023年より検索事業の事業責任者に就任。2025年3月より現職。
藤門千明(以下、藤門) 私自身も個人で事業を始めたときに、印刷EC「ラクスル」で名刺を作ったことがあります。そのときは「一般的なカスタマイズECなのかな」と思っていたのですが、今回ジョインしたことで印象が変わりました。当社が展開するサービスはどれも、事業ドメインごとの意味やプロセスの深い理解がなければ提供できないプロダクトなんです。
竹内 そこはまさに当社の特徴であり、強みだと思っています。社内ではよく「解像度」という言葉で表現するのですが、印刷、マーケティングといった各事業ドメインにおいて、それぞれのメンバーが高い解像度を持って取り組んでいるんです。そうして深掘りすることで、各事業ドメインの中に潜む非効率・非生産的なプロセスを発見し、そこに対してDXを徹底的に仕掛けていく。
例えば、「ノバセル」はテレビCMにおける情報の非対称性を解消して広告主をエンパワーすることで、マーケティングの民主化を目指しています。
──最近では金融プラットフォーム事業への参入も発表されましたね。
竹内 金融プラットフォーム事業も同じ考えに基づいています。中小企業にとって決済はビジネスの生命線でありながら、非効率・非生産的な要素が多く存在しているのが現状です。
藤門 事業を深堀りし、課題を解決し、価値を提供する。それこそが当社のこれまでの成長を支えてきた強みですよね。
竹内 この強みは今後も大切に育てていきたいと思っています。一方で、当社が次の成長フェーズに入るにあたり、乗り越えなければならない課題も見えてきました。

“サイロ化”してしまった各サービスを「RAKSUL ID」で連携する
──今、どのような課題に直面しているのでしょうか。
竹内 各事業のメンバーが、それぞれのドメインにおいて高い解像度を持ってサービスを提供してきた結果、事業ごとの連携が薄れ、“サイロ化”が進んでしまいました。
それぞれの事業・サービスは独自に成長し、お客さまにも支持されています。しかし、全体として「なぜこれほど幅広い事業展開をしているのか?」と問われると、一貫したストーリーが見えにくくなっていると感じています。2024年には、この点が経営課題としても浮上し、私たち自身も改めて事業のつながり方を見直す必要があると認識しました。
──たしかに……。事業の幅が広がると、お客さまの中には、それぞれのサービスが同じ企業によって提供されていることを認識していない方もいるかもしれません。また、各サービスの連携による利便性や価値を実感しにくかったり、提供元が一貫しているからこそ得られるメリットを十分に感じられていなかったりすることも考えられますね。
竹内 では、この課題をどのように解決していくのか。シンプルに言えば、各サービスをシームレスに利用できる環境を整える必要があります。そのためには、ワンストップでサービスを提供できるプラットフォームが不可欠です。そこで、各サービスIDの統合プロジェクトを推進するために、藤門に参画してもらいました。
藤門 IDや決済領域は、私がこれまでのキャリアで専門的に取り組んできた分野です。IDは単にユーザーを識別し、サービスにログインしてもらうための仕組みではなく、本質的な価値は、複数のサービスをシームレスにつなぎ、より良いユーザー体験を提供することにあります。
私自身、これまでIDを統合し、サービス間の連携を強化することで、ユーザー体験が大きく変わり、事業の成長にも直結すると実感してきました。今、私たちは同じようなフェーズにいて、これまでの経験を生かしながら新たな挑戦をしていきたいと考えています。
──竹内さんはこれまでどおり各事業の深化を担い、藤門さんは共通ID基盤構築を担当されるということでしょうか。
竹内 はい、その体制で進めていきます。今後の技術戦略やプロダクト戦略の根幹となるのが、この共通ID基盤の構築です。藤門にはこのプラットフォームの設計・開発を託し、各事業の技術戦略については、引き続き私が責任を持つ形で役割分担をしていきます。

──共通ID基盤ができると、サービスやユーザー体験にはどのような変化が起こるのでしょうか。
藤門 一つのIDで複数のサービスを利用できることは、お客さまにとって大きな利便性をもたらします。
例えば、店舗を開業する際には、名刺を作り、ハンコを用意し、チラシを作ってポスティングする……など、さまざまな準備が必要になります。これまでは、それぞれのサービスを個別に依頼する必要がありましたが、IDを統合することで、これらのプロセスをワンストップで実現できるようになります。
さらに、統合されたIDを通じて、お客さまのデータがリアルタイムで蓄積されるため、サービスを横断した提案や、タイミングに合わせた適切なご支援が可能になるでしょう。一つのIDを作成してもらえれば、中小企業の皆さまの事業をより加速させられる。そういった世界観を生み出すことができると考えています。
サービス間の連携はトラブルや「空白地帯」が生じやすい

──すでにデータ連携は進んでいますか。
竹内 一部のサービス間では連携が進んでいますが、全体としてはまだ十分とは言えません。これまで、データ連携を戦略的に設計してこなかったことが要因だったと考えています。全サービス間のシームレスな連携を実現するためには、明確な方針と技術的な基盤が必要なので、現在まさにその準備を進めている段階です。
──これだけのサービスがあると、連携は簡単なことではないですよね。
藤門 そうですね。私自身も前職で経験しましたが、複数のサービスを横断的につなげようとすると、さまざまなトラブルが発生することがあります。例えば、異なるデータを1カ所に集めて、データ解析ができるようにした場合、もともとそれぞれのサービスが同時に動くことを前提に設計されていないため、連携部分でボトルネックが発生し、システムが正常に機能しなくなってしまうことも考えられます。
さらには、縦軸(事業ごとの最適化)と横軸(全社的な統合)の優先順位が必ずしも一致しないという問題もあります。事業単位では、短期的な成長を優先してスピード感を持って進めたい一方で、全社的な統合には長期的な視点での調整が必要です。この違いが、プラットフォーム化を進める上で大きな課題となります。実際、多くの企業がサービスのプラットフォーム化に取り組んでいますが、こうした利害の対立が壁となり、スムーズに進められないケースが少なくありません。
──それらの課題を解消していくにはどうすればいいのでしょうか。
藤門 まず、私たち経営層が、「なぜ横断的な基盤が必要なのか」「なぜ今、このタイミングで共通基盤を整備すべきなのか」を、現場としっかりコミュニケーションをとりながら、説明責任を果たすことが重要です。
その上で、各事業のどの部分をプラットフォーム化するのかを慎重に見極めなければなりません。というのも、事業が持っている機能をそのままプラットフォームに寄せていくと、プラットフォームが重厚長大になっていきます。それ自体はいいことですが、あるタイミングで手を加えたときに「この機能を変えると、別の機能に大きな影響が出る」といった事態が起きやすくなるんです。適切なバランスを取ることで、柔軟かつスケーラブルな仕組みを作ることができます。
──現場の意識改革や、システム連携のバランスを取ることがポイントになるのですね。
藤門 はい。トラブルを防ぐには、誰かが明確にリーダーシップを持ち、全体の方向性を決めることが不可欠です。責任の所在が曖昧なまま進めると、統合が中途半端になり、結果として“空白地帯”が生まれてしまいます。例えば、「この領域はどの部署がオーナーシップを持つべきなのか」といった認識のズレが発生すると、後々大きな問題につながることもあります。
こうした空白地帯をいかに早く見つけられるかは非常に重要です。早期に見つけ出し、スムーズに進められるよう、私が旗振り役を務め、全体の調整を行っていきます。
事業の深化と横断的基盤整備の狭間で「健全なコンフリクト」を起こす
──共通ID基盤の整備について、どういった構想で進められているか教えてください。
竹内 金融プラットフォーム事業を例に挙げましょう。金融の分野では強固なセキュリティや安定したオペレーションが求められます。その一方で、他の事業とシームレスに連携し、統一されたユーザー体験を提供するためには、セキュリティ性の高いID基盤をプラットフォーム化する必要があります。私の立場としては、安全性を担保しつつ、できるだけシンプルなUXを実現することが理想です。
しかし、当社には多様な事業が存在します。例えば、カスタマイズECで求められる“正しいUX”と、金融プラットフォームで求められる“正しいUX”は異なってくるはずで、それを踏まえた上で、適切なプラットフォームを作り込めるかが重要です。その点については、私から藤門にさまざまなリクエストを投げかけることになるでしょう。
──事業の深化(個別最適)と、全体を見据えた横断的な基盤整備(全体最適)の両面から議論を重ねていくということですね。
竹内 そうですね。私の視点は意図的に個別最適を強調したものになります。しかし、その視点がお客さま全体にとって正しい体験になるかというとまた違う話でしょう。そこは全体最適の視点から、藤門に適切なプッシュバックをしてもらいながら進めるべきだと考えています。「どのような技術が必要か」「どのようなプラットフォームであるべきか」、さらに言えば、「RAKSULグループとして何が正しいか」と言った観点で、健全なコンフリクトが発生することを期待しています。
藤門 具体的な技術選定については、グループ全体で完全に統一するつもりはありません。各事業にはそれぞれ異なるスピード感が求められ、最適な技術スタックも異なるためです。したがって、事業ごとに適した技術スタックを採用して構わないと思っています。
その上で、どの技術を選べば最も生産性を高くできるのかについては、私の腕の見せ所でもあります。竹内と健全に“けんか”しながら(笑)、メンバーが最高のパフォーマンスを発揮できるような技術選定を進めていきます。
竹内 中小企業向けに新しい機能を次々追加しましょうという世界観だと、どれだけクイックにPoC(Proof of Concept、実現可能性を検証するプロセス)を回せるかが重要です。一方で金融プラットフォームだと堅牢性がより重要になる。当然、両者では技術スタックの選定は違ってくるはずですよね。
現在、当社ではRuby on Railsを使用していますが、中にはGoや、それ以外のソフトウェアスタックも増えてきています。また、プラットフォーム基盤としては、より堅牢なJavaや、実績が豊富で信頼性の高い技術を採用する可能性もあります。事業ごとの特性を踏まえ、最適な選択をしていきたいと考えています。

プラットフォーマーになる瞬間だからこその「挑戦しがいのある環境」
──今のフェーズは、エンジニアにとってどのような環境でしょうか。
竹内 私自身もエンジニア出身ですが、一つの会社の中で複数の異なる事業やサービスに関わり、さまざまなタイプの挑戦ができる環境は、なかなか得られるものではありません。よく若手のメンバーには、「どんどん社内でチャレンジしてほしい」と伝えています。
例えば、長年カスタマイズECに携わった後に新たなキャリアを模索する場合、当社では金融や、プラットフォーム構築といった異なる領域に挑戦することも可能です。いわば“社内転職”のような形で、多様な経験を積むことができる。これこそが、今の当社に広がる技術組織ならではの面白さだと思います。
藤門 私も、この環境は非常に魅力的だと思います。世の中には、単一のWebサービスを提供している企業はたくさんありますが、そこから事業を加速度的に拡大し、横断的にプラットフォーム化していくフェーズにある企業となると、極端に少なくなるでしょう。なぜなら、プラットフォーム化は決して簡単な話ではなく、企業としての大きな覚悟が必要になるからです。
私は、プラットフォーム化とは“ビジネスのフェーズを一段上げる”ことだと思っています。巨大なプラットフォーム企業も、スタートアップからメガベンチャーへと進化する過程を経てきました。同じように、当社も中小企業向けのプラットフォーマーとして、大きくステップアップしようとしています。その瞬間に立ち会えるのは、エンジニア人生において貴重な経験になるでしょう。

──エンジニアにとっても唯一無二のチャレンジができるチャンスですね! どのようなエンジニアに来ていただきたいですか。
藤門 当社では、よく「インパクトを生み出せるのか?」という問いが交わされます。これはジュニアからシニアエンジニアまで、皆が意識して口にしているキーワードです。今や、テクノロジーを活用してプロダクトを作ること自体は、以前ほど難しいことではありません。生成AIなどの技術が進化し、一定レベルのものは短時間で構築できる時代です。しかし、それだけでは十分ではありません。本当にユーザーや社会に対してインパクトを生み出せるかどうかが、エンジニアとして問われるべき本質です。
単にテクノロジーを扱うだけでなく、それをどう活用し、どのように価値を生み出すのか。この「テクノロジーの力でインパクトを生み出す」ことこそが、当社の文化であり、マインドセットです。技術は時代とともに変わりますが、このマインドセットは変わることがありません。そのため、技術を良い意味での手段として捉え、それを活用して事業や社会にどのような変化をもたらせるのかを深く考えながら取り組む姿勢を持てる方と、共に挑戦していきたいと考えています。
竹内 当社が取り組んでいることは、単にDXと表現することもできますが、それだけでは不十分だと考えています。目指しているのは、より深いレイヤーでの変革と、実世界に対する大きなインパクトの創出です。そのために、事業設計の段階から共に考え、推進していけるエンジニアを求めています。
各事業ドメインにおいても、価値提供のアプローチは異なります。例えば、個々のサービスではお客さまに直接向き合い、最適な価値を届けることが求められます。一方で、基盤整備の観点では、組織全体としてどのようにメリットを最大化できるかを追求し、より大きなインパクトを生み出すことが重要です。
私たちは、単に技術力が高いエンジニアを求めているのではありません。重要なのは、テクノロジーを活用して実際のビジネスや社会にどのような価値を提供できるかを深く考え、それを形にできることです。その視点を持ち、実践できるエンジニアと共に働きたいと考えています。
ビジョンである「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」を体現し、テクノロジーの力で世の中をより良くしていくことに挑戦したい方をお待ちしています。
📢 RAKSULグループではエンジニアを募集しています!🌈
RAKSULグループの技術組織や働き方に興味を持っていただいた方は、ぜひ採用サイトをご覧ください。
▼ 求人一覧はこちら
職種ごとの求人情報を掲載しています。
▼ 会社紹介資料はこちらをご覧ください
[タイアップ広告] 企画・制作:はてな
取材・構成:山田井 ユウキ
撮影:関口 佳代