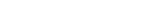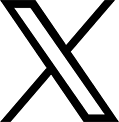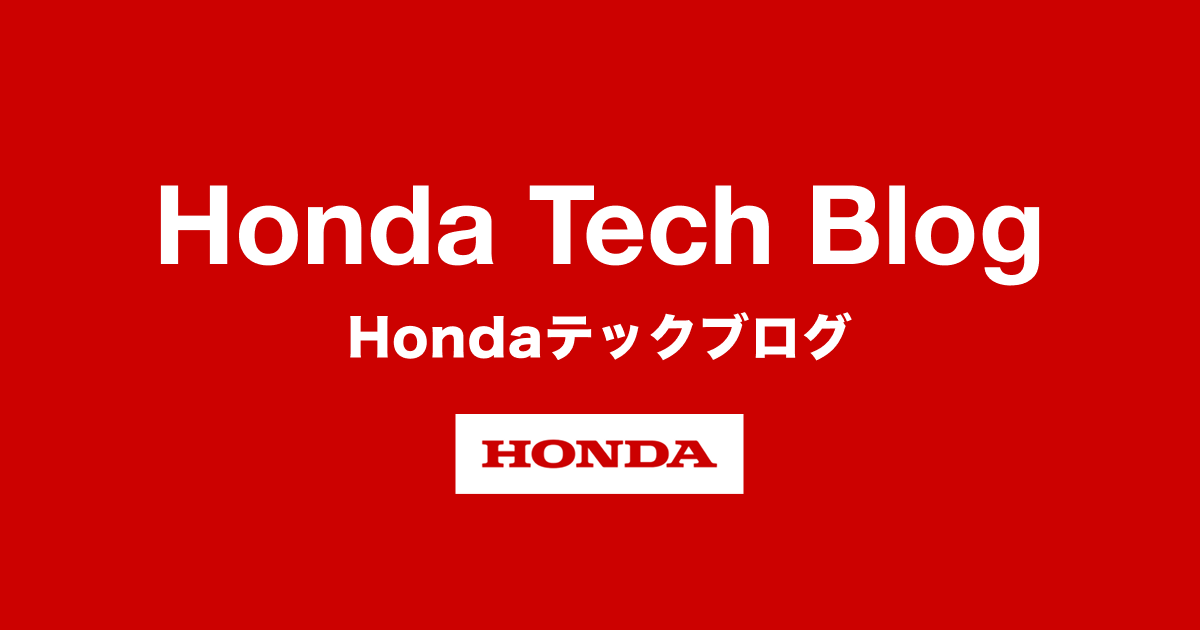自動車業界は現在「100年に1度の変革期」にあると言われ、SDV(Software Defined Vehicle)という考え方が注目されています。SDV、すなわち「ソフトウェアによって定義されるクルマ(Vehicle)」の実現により、搭載されるソフトウェアを後から追加・改善することで自動車を継続的に進化させることが可能になります。
SDV実現に必要なのが車両と外部を接続するコネクテッド技術です。技術革新に挑戦するHondaではこの分野でも、日本において専用の車載通信モジュールを主体とする『Honda CONNECT』を2020年に開始し1、その後の新型車・フルモデルチェンジ車に順次搭載しています。ここで注目されるのが、車載モジュールと接続するサーバーサイドのソフトウェア技術です。
例えば、スマートフォンからクルマを操作する。自動運転の地図を更新する。そのようなドライバーに役立つサービスがサーバーサイドで動作しており、その構築を手掛けるのがコネクテッドソリューション開発部(CSD)です。
今回は、そのサービス基盤をクラウドネイティブに設計・開発するソリューションアーキテクトグループの竹原洋三さん・川崎仁嗣さん・元木康貴さんの3人に話を伺いました。それぞれIT業界出身の知見を生かして、ソフトウェアの力で自動車のあり方を変革しようとしています。
※この記事は本田技研工業株式会社によるタイアップ広告です。
- コネクテッドの基盤を提供しつつ指針を示すチーム
- スマホアプリとクルマはどうつながっているのか?
- クルマを後から進化させるには?
- AWSのマネージドサービスを積極的に活用
- ソフトウェア開発者としての働き方と知見の共有
- ソフトウェアの力で「ものづくり」に貢献する仕事
コネクテッドの基盤を提供しつつ指針を示すチーム
── 早速ですがコネクテッドソリューション開発部のソリューションアーキテクトグループの皆さんは、Hondaの中でどのような業務を担当されているのでしょうか。
竹原:
まずコネクテッドソリューション開発部では、社内のコネクテッドに関する案件についてその開発と運用を手掛けています。その中でも私たちソリューションアーキテクトグループは上流設計の課題や、新しい技術の調査にアサインされるチームです。
私たちの業務の屋台骨になっているのがクルマにつながるサーバーで、これは大きく3つあります。1つがコネクテッドサーバーで、モバイル端末などを使ってクルマを遠隔操作するようなときに活用されるお客様寄りのサーバーです。
もう1つがOTA(Over The Air)で、スマートフォンなどと同じように無線通信を使って車載ソフトウェアをアップデートするサーバーですね。最後の1つが、いわゆる自動運転などの先進運転支援システム(ADAS:Advanced Driver-Assistance Systems)をサポートするサーバーです。
今回、グローバルコネクテッドサーバーから元木、OTAから川崎、グループリーダーである私の3名が来ています。

竹原 洋三
同グループリーダー
大手電機メーカーでのカーナビ開発とスマホ連携開発の経験を経て、自分でデジタルサービスを創るため2013年にHonda入社。ハードウェアとスマホアプリの経験を活用しつつ、サーバー開発に領域を拡大。Honda初のAWSをフル活用したマルチリージョンコネクテッドサーバーを企画・開発。コネクテッドカーのグローバル化に貢献した。さらに2021年から2024年まで北米駐在を経て、グローバルに業務を展開中。
── コネクテッドを利用するプロダクト、例えばクルマの遠隔操作アプリに対してインフラを提供するチームだけではないということですよね。
竹原:
その側面もありますが、SDVによるソフトウェアシフトは自動車の設計や作り方、サービスを含めたビジネスモデルを変える動きです。自動車業界の変革に対してHondaはどのようにやり方を変えていくかを、クラウド側から提案する役目があります。
例えばリコール対応などで車載ソフトウェアを更新しなければならないとき、これまでのようにお客様のお時間を頂き、クルマをディーラーに持ち込んで書き換えさせて頂く必要がありました。これをOTAで代替することはありますが、そうした複雑な要件をシステムに落とし込むことはかなり難しいですね。
さまざまな部署がコネクテッドで実現したいこと全てを実装すると統一性を欠いたシステムができてしまいますから、私たちはシステムの観点からプロダクトのオーナーである他部署に対して「こうやればできる」とか「こうあるべきだ」という提言をしています。
── なるほど。インソースとして社内の各部署にコネクテッドのあるべき姿を伝えて、それに沿ったプロダクトの提案・設計までを含めて担当しているわけですね。
スマホアプリとクルマはどうつながっているのか?
── 担当されている具体的なプロジェクトの話をお聞きしたいのですが、まずコネクテッドサーバーの役割や構成について教えてください。
竹原:
クルマがつながるネットワークの先にコネクテッドサーバーがあり、まず世界全域で共通のGTC(Global Telematics Center)サーバーが配置されています。実際にはクラウド上でアメリカ・日本・欧州などのリージョンごとに別々のインスタンスが起動して、その先にある各国の現地法人が運営するRTS(Regional Telematics Server)サーバーと一緒にサービスを提供しています。
── グローバルと地域を分けることで、アプリやサービスの地域差を吸収するイメージですね。アプリからクルマまではどのようにつながるのでしょうか?
元木:
地域のモバイルアプリはRTSに接続します。直接GTCというケースも一部ありますが、アプリがRTSに接続して、RTSがGTCのAPIを呼び出し、GTCがコマンドを送ってクルマを操作するのが現在では主流のパスです。
この構成になっていることで、アプリ側からも車種による違いをあまり意識しないですむように、GTCが抽象化したAPIを用意しています。
AWS(Amazon Web Services)の世界7リージョンで、CloudFormationなどの技術を利用してマルチリージョンデプロイを実施することで、同じGTCのソフトウェアが起動できるようにしています。

元木 康貴さん
同グループ 主任
公共系のSIerを経て、自社プロダクト開発と新しい技術への挑戦のため2020年にHonda入社。2021年にコネクテッドCCoEにメンバーとして参画。2023年から次世代コネクテッドプラットフォームの企画開発を推進する。
── コネクテッドサーバーの構築を通して挑戦ややりがいを感じる仕事は何でしょう。
元木:
一般的なソフトウェアエンジニアから見て特殊なところとしては、やはり車両というハードウェアがあるところです。車両ごとにできることも違っていて、車種によって機能が違っていたり、車種が同じでも世代が違えば全然変わっていたりします。
そうした車両ごとの制約を踏まえつつ、ソフトウェアやプラットフォームとしてはどんどん進化していかないといけない。それを両立させることが、私たちのようなコネクテッドのアーキテクトには一番チャレンジングで、やりがいのある仕事になります。
── 例えばもっと手軽なスマートフォンなどは毎シーズンのように新製品が出て、それにシステムが対応していきますが、そういった形をイメージするとよいでしょうか。
元木:
車両は走行するハードウェアですから安全に関わる制約もありますし、スマホ以上に長く利用されるものなので古いモデルも扱えなければいけない。そうした要素も含めてチャレンジングだということは言えるかもしれません。
── そうすると古い車種に新しい機能を追加することも必要になってくるわけですね。
川崎:
昔の車載モジュールは本当に必要な機能しか実現できなくて、そもそもアップデートする余地がありませんでした。しかし、最近では事前に十分な性能を持たせることで、後から機能を追加できるようになっています。スマホのように、ソフトウェアの力で継続的に進化するクルマがこれから現れます。

川崎 仁嗣さん
同グループ 主任
大手携帯通信事業者を経て、100年に1度と言われる大変革期の自動車業界にて新たな挑戦をしたく、2021年にHonda入社。入社当初から一貫してOTAのクラウド側プロダクトを担当。2023年から次世代OTA向けクラウドプラットフォームの企画開発推進を担当。
クルマを後から進化させるには?
── 進化するクルマという話が出ましたが、これはOTAの領域になりますね。
川崎:
はい。竹原が説明したようにクルマにつながるサーバーにもいくつか種類がありますが、私はOTAと呼ばれる、車両ソフトウェアの更新に関わるサーバーと、そのシステム周りのソリューションとアーキテクチャ設計を担当しています。
OTAのシステムは、元木が述べた情報コンテンツやアプリのサービスを提供するコネクテッドサーバーとは別に構築しています。OTAサーバーもクルマから直接つながるのでグローバルな存在で、GTCとは異なりグローバルに対して1リージョンで運用しています。
── 自動車のソフトウェアを出荷後にアップデートするにはこれまで物理的な作業が大変でしたが、現在ではクラウドからダウンロードとインストールが可能になっているわけですね。現状、OTAではどのようなソフトウェアを更新しているのでしょうか。
川崎:
不具合対応については、Hondaは全てOTAで実施する方針になっています。これまでのモデルでもOTAは入っていて、例えば2020年モデルの「レジェンド」から自動運転の不具合対応やリコール対応にも利用できるようになっています。
そしてこれからは機能拡張やサービスの更新などにも対応します。Honda 0(ゼロ)シリーズから機能アップデートが配信されるようになり2、スマートフォンのアップデートと同様に通知がユーザーに届き、許諾に同意すれば自動的に書き換わります。
社内では「後から進化」などと呼ばれていますが、OTAを開発している私たちだけではなく全社的に取り組んでいます。
── OTAにおいてチャレンジングなことは何でしょうか?
川崎:
OTAではサーバーを構築するだけではなく、車両の構成管理も行っています。このモデルの部品であればソフトウェアのアップデートが必要だけど、これは必要ではない、といったことを部品表をもとに管理しなければいけません。
そのため部品を作る工場やサービス保証しているアフターセールスの部門など関係者が多くなることは大変ですが、逆にそれだけ大きな仕事でもあるので、全部をまとめて最後に正しく動作したときの達成感はかなり大きいですね。

── リコール対応も含むということは、法規的な理解も必要になりますね。
川崎:
そうですね。OTAサービスを搭載する車両には、メーカーの開発体制や車両側の機能要件など法律3で定められた基準があります。セキュリティ要件や安全基準を満たしていない車両は、国の認証を得ることができません。
従来では車両本体の安全性が基準でしたが、OTAシステムではサプライチェーン全体のセキュリティ要件や組織体制も求められますから、それに沿った開発を行っています。
また、ソフトウェアアップデートのトレーサビリティも求められるので、全ての履歴やログを記録し、データ消失を防ぐための対策を講じています。
AWSのマネージドサービスを積極的に活用
── AWSでクラウド構築している話が何度か出ていますが、もう少し詳しくお聞かせ頂けますか。AWSはいつから利用されているのでしょうか。
竹原:
2013年ごろです4。コネクテッド事業を全世界に広げるためにクラウドの検討を始めました。クラウドがまだそれほどメジャーではなかったこともあり、少ない選択肢の中で要件を満たせるサービスがAWSでした。
── Hondaでは、その前から独自のナビゲーションシステム「インターナビ」でいち早くプローブカー(自動車の走行情報を集約するシステム)の機能を実現されていましたね。
竹原:
オンプレミスだったインターナビをベースに、グローバル展開を目指していち早くクラウドの活用を決定し、2015年にサービスを展開しました。このような迅速な実現にはオンプレミスではなく、クラウドのスケーラビリティがなければ無理だろうと考えました。
── どのようにAWSの活用を広げていったのでしょうか。
竹原:
最初は東京リージョンだけで構築しましたが、かなり改善の余地があるシステムでした。それをAWSと一緒に、次の世代、次の世代と改善していく中でマネージドなコンポーネントの利便性に注目しました。例えばAmazon API GatewayやAWS Lambdaなどが登場してきたときも、いち早く導入を決定してきました。結果、安定性は劇的な改善を見ることができました。
オンプレミスのサーバーをただクラウドに移管するのではなくクラウドネイティブな構成にしたいという私たちのニーズと、AWS側の「これが必要だろう」というシーズが合致して、とてもタイムリーに構築できたという経験があります。

── コネクテッドでもOTAでも世界の複数のリージョンで同じソフトウェアをグローバルに動作させるという話でしたが、工夫されていることはありますか。
元木:
そうですね。同一構成によるインスタンスを、リージョンごとに安定して稼働させなければなりません。機能変更などがあれば、テスト環境での試験から本番環境へのデプロイまで、迅速かつ正確に行う必要があります。
我々のサーバーは竹原が話したAmazon API GatewayやAWS Lambdaをはじめ、AWS IoT CoreやAWS Fargateなど多くのコンポーネントから構成されており、またリージョンによって異なるパラメータで稼働させています。これら全てを手動管理するのは現実的でないため、AWS CodePipelineなどを活用したCI/CDの自動化を行っています。
構成もAWS CDK(Cloud Development Kit)を使って、コードで管理・構築しています。
── OTAのサーバー構築についても教えてください。
川崎:
OTAサーバーはコネクテッド技術でも特殊な役割を持ち、ソフトウェア更新をオンデマンドで処理する必要があります。サーバーインスタンスを常時稼働させる必要はありませんが、リクエスト発生時に即座に処理を開始できなければいけません。そこでイベント駆動型のAWS Lambdaを活用し、サーバレスのアーキテクチャで構築しています。
リコールの場合などは対象車両ごとの一斉更新となるため、トラフィックが集中する可能性があります。回線やサーバーの負荷なども考えなければならず、Lambdaのようなサーバレスの仕組みは不可欠ですね。
── ほかに自動車特有のAWSコンポーネントの使い方はありますか?
竹原:
テレマティクスサービスの車両データのやりとりに使用できるAWS IoT Coreも、リリースされたときにすぐ使い始めました。デバイス間の通信において軽量でセキュアな通信ができるMQTT(Message Queuing Telemetry Transport)も、コネクテッドカーとの親和性が高いプロトコルだと思います。
これもプロダクト側からクルマとの迅速な通信の要望があり、HTTPよりもMQTTを利用した方が適していると判断し、私たちから提案した経緯がありますね。
元木:
今後のクラウド利用という点では、車両の開発を全てクラウド上の仮想空間で行えるサイバーフィジカルシステムを作ろうとしています。DPG(Digital Proving Ground)という取り組みですが、車両の各ECUのソフトウェアをクラウド上で動かし、1台の車両を再現します。
── それが実現すると本当に車両のソフトウェア開発が可能になりますね。
お話を伺っていて、AWSでリリースされる最新のマネージドサービスをいち早く活用したりトライしたりできることも、Hondaならではの魅力だと感じました。
ソフトウェア開発者としての働き方と知見の共有
── システムの設計と構築が業務の中心になっているかと思いますが、自身でコーディングなどはあまりされないのでしょうか?
元木:
現在コーディング作業などは協力企業にお願いすることが多いです。ただ実装も分かっていないと、最適なアーキテクチャの検討やパフォーマンスの最適化などは難しく、仕組みに対する理解と俯瞰的な視点のバランスが求められます。
川崎:
OTAで配信したソフトウェアが正しくインストールされて動作するかを、海外に出張してチェックすることもあります。現地で不具合やミスが見つかればその場で検証環境のソースコードを修正して、その結果を開発ベンダーにフィードバックすることもあります。
── 確かに自動車メーカーですから実環境での開発や検証も必要になるのですね。
川崎:
新しいソフトウェアをテストするときにシミュレータやモデルベースで検証することもありますが、ときには実車を使ったテストや、テストベンチ(作業台)で検証する必要が発生して、栃木の開発拠点で作業することもあります。
── 皆さん前職はIT業界ですが、自動車の開発に関する知識は入社されてからキャッチアップされたのでしょうか。
竹原:
CSDの中途採用メンバーはほとんどがIT業界からの転職です。そのため自動車の設計や、業界のプロセス、ゲートと呼ばれる工程ごとの進捗管理は、全く新しい領域の知識です。そこで我々の部門では専門技術の教育・研修システムなどを用意して、すぐにキャッチアップできるようにしています。
さらにコネクテッドやソフトウェアシフトは全社で取り組んでいるミッションなので、さまざまな部署から「こうしたことは実現できないか?」と相談を受けることも多いです。幅広い経験や知識がある仲間に恵まれているので、こちらから逆提案していくこともあります。入社前に自動車業界での経験がなくても十分に仕事ができますね。

── 開発言語も一般的なものを採用しているのでしょうか。
元木:
とくにこれと決まったものはありませんが、AWSのマネージドサービスとの親和性からPythonやTypeScript、そのほかにはJavaなどをよく使っています。
── 先ほど自動車のセキュリティ要件という話がありましたが、構築するAWSなどクラウドのセキュリティ要件も大切になりますね。
竹原:
開発に必要なセキュリティやガバナンスは、クラウドCoEによるクラウド管理体制を導入して共通のガードレールがあり「知らないうちに誰かがS3を全公開にしていた」ということは起きないようになっています。
── クラウドCoE(Center of Excellence)ということは、クラウド戦略に必要な知見や経験を持ってそれを担っている方がいるわけですね。
元木:
はい。私はコネクテッドサーバーを開発しながら、CCoEとして部内のクラウドソリューションを推進する役目も担っています。
私たちの組織はいま中途の方を採用して急激に大きくなっているので、新しく入ってきた方を含めて安全に開発できる最低限のガードレールは共通で敷いていますね。
川崎:
AWSのアカウントはプロダクトごとに別々ですが、セキュリティのために必要な設定はそれほど変わらないですね。CCoEのガイドラインでこれまで個別に準備していたセキュリティ要件が共通化され、削減できた工数もあります。
元木:
ガードレール以外でも、コネクテッドのプラットフォームにおけるクラウド設計のベストプラクティスやアーキテクチャパターンなどをナレッジ化して共有しています。
プロダクトごとに検討すると時間がかかるような知見、例えばAWSでいうとコンピューティングサービスであるLambdaとFargateをどう使い分けるかなどを、ナレッジとして展開しています。設計の工数を大きく削減できたプロダクトがあるとも聞いています。

ソフトウェアの力で「ものづくり」に貢献する仕事
── 最後に、自動車業界でやってみたいと思っているITエンジニアの方にメッセージがあれば、それぞれお願いします。
元木:
私はSIer出身ですが、Hondaの最大の魅力は自分たちのプロダクトを多くのエンドユーザーに届けていることです。ただ要求されたものを作るのではなく、自らプロダクトを良くしていける喜びがあります。また、何百万ものユーザーが利用するプラットフォームづくりやその意思決定に関われる点も、私たちの仕事の大きな魅力です。
川崎:
通信事業者は基本的に国内市場のための機器やサービスを手掛けますが、Hondaはグローバル企業なので世界で活躍ができる点が魅力です。自分たちが手掛けたシステムやプラットフォームがワールドワイドに展開される。海外出張を通じて現地のエンジニアとも協力しながら仕事ができる。海外志向のある人にも面白い職場だと思います。
竹原:
時代は確実にSDVに進んでいます。自動車の機能や価値が、ソフトウェアやサービスの側面から評価されることになります。自動車本体の性能だけでは完結せず、クラウドや外部サービスと連携しながら製品を作っていく流れがあります。
その意味で、ソフトウェア開発の能力を持ちつつ「ものづくり」にも興味ある人が活躍できる領域です。クラウドアーキテクチャと次世代のクルマづくりに貢献できる仕事です。
── まさに次世代のソフトウェアで定義されるクルマそのものを作っていくことになる方々がここにいるのだなと感じました。興味深いお話をありがとうございました。
🚗 Hondaではソフトウェアエンジニアを積極募集中 💡
興味のある方は下記のサイトからご応募ください。
Hondaのソフトウェア開発に興味があるなら、ぜひこの3月に開設されたテックブログや、内製化チームによるQiitaもご覧ください。

[タイアップ広告] 企画・制作:はてな
取材:中尾 真二
撮影:関口 佳代
- 参考:Honda公式サイト「新世代コネクテッド技術 Honda CONNECT」↩
- 参考:Honda Stories「【5分で読み解く】Honda 0シリーズが切り開く移動の新たな可能性」↩
- 例えば、国連のUN-R155(サイバーセキュリティ)やUN-R156(OTA更新)があり、国内では「道路運送車両法」改正により型式指定要件にサイバーセキュリティとOTA要件が追加された。↩
- 参考:TECH PLAY Magazine「Hondaが取り組むAWSアーキテクチャ刷新の変遷、モビリティ・グローバル・サービスをつなぐスケーラブルな構成とは」↩